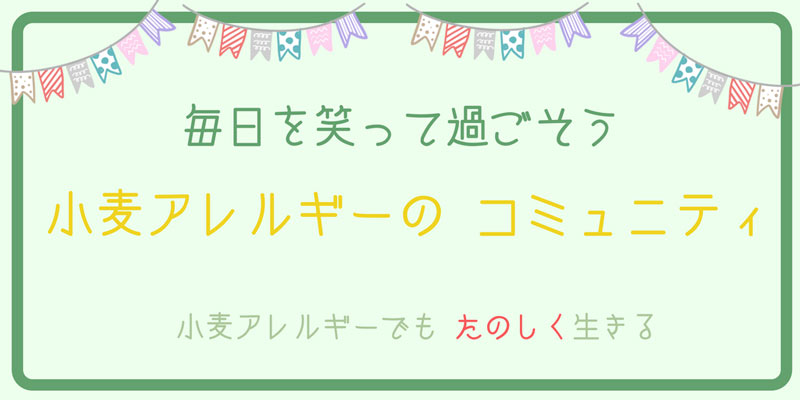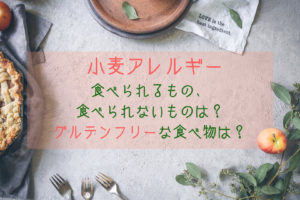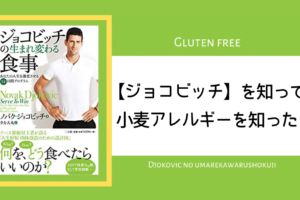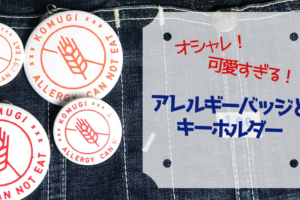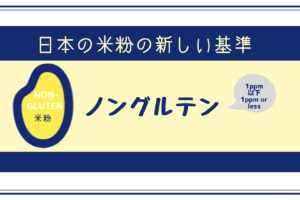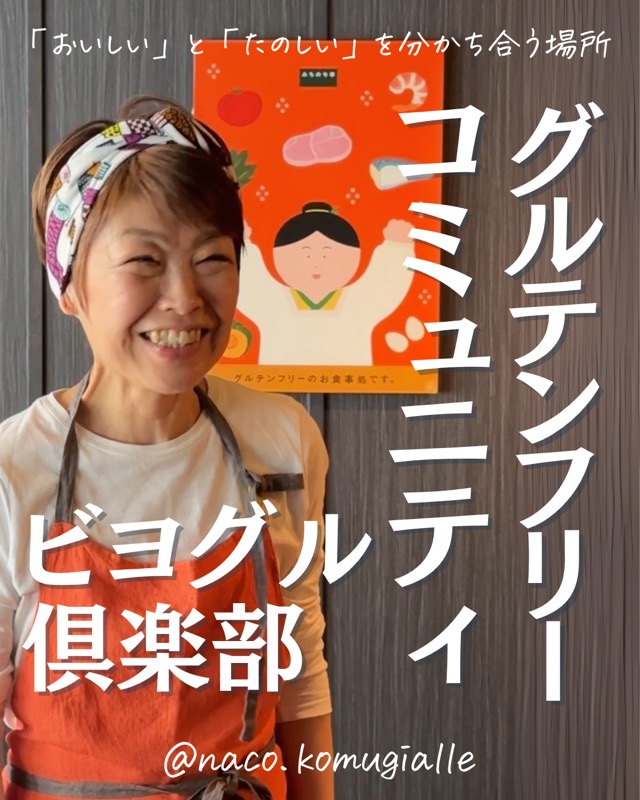グルテンフリーや小麦アレルギーをお持ちの皆さんは、新しい「アレルギー対応スイーツ」を見つけても本当に安心して食べられるのか不安に感じた経験はありませんか?
「小麦不使用」と書かれていても、共通の施設で製造されている場合、微量なコンタミネーション(アレルギー物質の混入)が心配になりますよね。実は、共通施設での製造におけるアレルギー対応には様々なケースがあり、判断がとても難しい問題です。本記事では、その難しさの理由と具体例、そして安全に楽しむために私たちにできることを、自身が重度の小麦アレルギーを持つnacoの視点からお伝えします。
同じ悩みを持つ方がこの記事を読むことで、きっと共感するとともに、グルテンフリー対応の商品を選ぶ際のヒントや安心材料が得られるはずです。
結論としては、最終的には自分自身で情報を集めて判断することが必要ですが、そのために何を確認し、どう向き合えば良いのかをご一緒に考えていきましょう。

もくじ
アレルギー対応表示と「共通施設で製造」の現実
食品を選ぶとき、ラベルに「小麦不使用」「グルテンフリー」と書いてあるとホッとしますよね。しかし、その注意書きに「本製品は小麦を含む製品と共通の設備で製造しています」といった一文を見つけると、一気に不安になる方も多いでしょう。実際、この「共通の施設で製造しています」という表示は曲者で、どの程度しっかりアレルゲン対策が取られているかはケースバイケースなのです。
例えば、過去に私が体験したケースでは、「原材料に小麦粉は使っていません」と説明されたグルテンフリーと記載された米粉パンを食べてアレルギー症状が出てしまったことがありました。
後からメーカーに確認すると、案の定そのパンは小麦を使ったパンと同じ工場で製造されていたんです。原材料欄に小麦の表示がなくても、同じラインで作られていれば微量の粉が混入してしまうことがあります。
一方で、「小麦製品を扱う共通の施設で製造しています」と明記されている場合でも、必ずしも危険だとは限りません。企業によっては細心の注意を払って対策をしているところもあります。例えば、あるメーカーの卵不使用マヨネーズの商品には「卵を使用した商品と同じ施設で製造していますが、十分な洗浄を行ってから製造しています」と記載されていました。このようにきちんと対策を書いてあると、「そこまで気をつけてくれているなら大丈夫かも」と少し安心できますよね。


コンタミネーションへの不安と見えないリスク
共通の施設で製造された食品で一番怖いのは、やはりアレルゲンのコンタミネーション(微量混入)です。特に小麦粉のような粉状の原料は空気中に飛散しやすく、調理器具や設備の隅々にまで残りがちです。例えば、通常のラーメン店で提供される「グルテンフリー麺」を考えてみてください。茹でる前の麺には互いにくっつかないよう小麦粉の打ち粉がたっぷり付いています。その麺をほぐしただけでも粉が舞い散り、厨房中に飛んでしまうんです。そうなると、どれだけ器具を洗浄しても完全に粉を除去するのはとても難しいでしょう。
同じことはパンやドーナツなど小麦粉を扱う食品全般に言えます。グルテンフリー商品を通常の製造ラインで作るリスクは、この「見えない微量の小麦」が最大の障壁なんです。私自身、小麦粉が舞う環境で作られたグルテンフリー食品は想像するだけで怖いなと感じてしまいます。「これ本当に食べても大丈夫かな?」と疑心暗鬼になるのは、きっと私だけではないですよね。


こちらは先述のグルテンフリードーナツ専門店の商品イメージです。米粉で作られた生ドーナツで、見た目も可愛らしくとても美味しそうですよね。小麦アレルギーの子ども達にもみんなと同じドーナツ体験をさせてあげたい、という想いから生まれたブランドとのことで、私もオープン前から期待で胸が膨らんでいました。ただ、公式には「通常店舗とは独立した専用の製造環境で作っています」と説明されつつも、実際には完全なコンタミネーションを排除することは難しいとも注意書きがあります。こうした情報を目にすると、「どの程度安全なのだろう?」と慎重にならざるを得ません。




専用工場が理想だけど…現実は難しい
「グルテンフリー専用の工場で作れば安心」というのは誰しも思う理想ですよね。確かに、設備も原材料もすべてグルテンフリー専用であれば、小麦の紛れ込みを心配する必要はなくなります。しかし、現実問題として専用工場を持つのはとても大変です。設備投資や維持費もかかりますし、ビジネス規模によっては専用ラインを作るのが難しい場合も多いです。
実際、多くのお店やメーカーは限られた設備の中で工夫しながらアレルギー対応をしています。例えば、とあるケーキ屋さんでは「小麦を使う日」と「使わない日」を分けて製造しているそうです。小麦使用日には通常のケーキを焼き、次の日には機材をすみずみまで洗浄した上で朝一番にグルテンフリーのケーキを作る…という徹底ぶりで、可能な限りコンタミネーションを減らしているとのことでした。それを聞いたとき、「そこまでしてくれるなら安心して買えるかも」と思わず嬉しくなりました。
私自身のお店(※名古屋で小麦・麦不使用の定食のお店「みちのり亭」を営んでいます)でも、小麦や麦類の持ち込みは一切禁止しており、調理スペースは完全にグルテンフリー専用です。おかげで小麦混入のリスクを限りなく抑えることができ、提供できていますが、この環境を維持する大変さも痛感しています。実は一時期、うちのキッチンをグルテンフリー製造をしたい他の方にシェア利用してもらえないか、と考えたこともありました。でもその場合、もし万が一でも小麦が持ち込まれてしまったら…と想像すると、リスクが高すぎて踏み切れませんでした。せっかく守ってきたこの環境を崩してしまう可能性を考えると怖いんです。
このように、グルテンフリー専門の環境を用意すること自体がハードルであるため、多くのメーカーは共通設備での製造を選ばざるを得ないのが現状です。その結果、「共通の施設で製造しています」という表示が増えるわけですが、大事なのはその裏でどんな工夫や対策をしているかですよね。


お店のアレルギー対応への姿勢を見極める
共通設備で製造された食品を口にしても安全かどうかは、最終的にはそのお店やメーカーのアレルギー対応への姿勢にかかっています。同じ「共通の施設」であっても、徹底的に対策しているところとそうでないところでは雲泥の差です。私たち消費者側としては、その姿勢を見極めるために情報収集をすることが重要になってきます。
一番手っ取り早いのは、やはり直接お店に問い合わせてみることです。勇気が要りますが、「小麦アレルギーでも大丈夫ですか?どのような対策をされていますか?」と尋ねてみると、その返答からお店の考え方が垣間見えます。丁寧に説明してくれたり、場合によっては「原材料のパッケージをお見せできますよ」とまで言ってくださるお店もあります。実際、私が問い合わせたあるカフェでは、使用しているマヨネーズ(卵不使用)の容器を見せてくれて、「これは卵アレルギーのスタッフも愛用している市販品です」と説明してくれたことがありました。そう言われると「あ、それ知ってる!私も食べたことがある!」と安心できますよね。
逆に残念なケースもあります。質問に対して明確な回答をもらえなかったり、「アレルギーの方には提供できません」と言われてしまうお店も実際に存在します。先日も、あるお店で詳細を尋ねた方が「それならアレルギーの人はご遠慮ください」と購入を断られてしまったという話を聞きました。それまでその方は普通に買っていた常連さんだっただけに、大きなショックを受けたそうです。「アレルギーの人お断り」という対応は、確かにお店側からすればリスク回避なのかもしれません。でも、軽度のアレルギーで少しのコンタミなら大丈夫な人まで一律にシャットアウトされてしまうのは悲しいことですよね。
私自身、重度の小麦アレルギーがあるのでお店選びには慎重になります。けれど、アレルギーの程度は人それぞれです。だからこそ、「どの程度気をつけているのか」「どんなリスクがあり得るのか」を事前に知りたいと思っています。それを聞いた上で「やっぱり無理だな」と思えば諦めますし、「それなら試してみようかな」と思えるならチャレンジもできます。
安全に楽しむために私たちにできること
結局のところ、自分の身を守るためには自分で動くしかないというのが現実です。特に重度のアレルギーをお持ちの方にとっては、初めて口にするものに対する不安は計り知れないですよね。「もし症状が出たらどうしよう…」という不安を少しでも減らすために、できることを整理してみましょう。
- 事前に情報収集する – お店の公式サイトやSNSでアレルギー対応について言及がないかチェックします。最近は「グルテンフリー」「アレルギー対応」を売りにするお店も増えているので、そうしたお店は積極的に情報を発信していることが多いです。
- 問い合わせてみる – 前述のように、電話やメールで直接質問してみるのは有効です。丁寧に答えてくれるお店なら信頼度アップですし、逆に明確な回答が得られなければ利用を見送る判断材料になります。
- 周囲の体験談を参考にする – アレルギーを持つ人同士のコミュニティやSNSで、特定のお店や商品の評判を調べてみましょう。「ここの◯◯は大丈夫だった」「△△で症状が出てしまった」等のリアルな声はとても参考になります。
- 少量から試す – もし買ったものを食べる場合は、いきなり全部食べずに少量から試してみるのも一つの方法です。特に初めてのお店の商品は、少し食べて様子を見ることでリスクを下げられます。
こうした工夫をしながら、「ここなら大丈夫」と思えるお気に入りのお店が見つかると嬉しいですよね。また、一度信頼できるお店が見つかったら、そのお店を応援することでアレルギー対応の輪が広がるかもしれません。




まとめ:慎重さと対話で広がる食の楽しみ


共通施設での製造とアレルギー対応の難しさについてお話してきましたが、最後に改めてポイントを振り返ります。
まず、大前提としてコンタミネーションのリスクはゼロにはできないことを私たち消費者側も理解しておく必要があります。その上で、「共通の施設で製造」の一言に過剰に怯えるのではなく、「具体的にどんな対策をしているのか?」を知ることが大切です。お店によって対応は千差万別ですから、疑問に思ったら遠慮せずに聞いてみましょう。もちろん聞く側にもマナーは必要ですが、真剣に尋ねればきっと真剣に答えてくれるお店もあります。
そして、もし問い合わせた結果「アレルギーの方にはおすすめできません」と言われてしまったら…それは残念ですが、そのお店は潔く諦める勇気も持ちましょう。それは同時に、「万全の対応ができないお店なんだ」と分かったということでもあります。一方で、丁寧に対応してくれるお店に出会えたら、その安心感は何にも代え難いですよね。
グルテンフリーやアレルギー対応の食品を取り巻く環境は、少しずつ良くなってきてはいますが、まだまだ消費者が神経を使う場面が多いのが現状です。それでも、私たち自身が声を上げ続けることで、お店側の意識も高まり、安心して食べられる選択肢が増えていくと信じています。
共通施設で作られたものでも、工夫と対話次第で安心して楽しめる世界はきっと広がります。同じアレルギーを持つ仲間として、これからも情報交換しながら、おいしくて安全なスイーツや食品を一緒に探していきましょうね。
最後までお読みいただきありがとうございました。皆さんのグルテンフリー生活が、少しでも笑顔あふれるものになりますように。